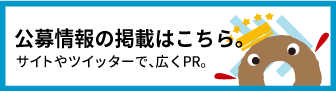こんにちは、またはこんばんは、まさかな(公募ストック運営・管理)です。また間が空いてしまってスミマセン。
本来なら今回は「物語文・小説文の読み方・解き方」の回なのですが、ちょっと寄り道をして、説明文・論説文の例文を書いて、その中身を説明してゆく回を設けたいと思います。
さっそく参りましょう。なお、物語文・小説文の読み方・解き方についても、本日中にアップ(4月5日)できればと思います。よろしくお願いします。
【小・中・高校生向け/作文・国語シリーズ・目次と予定】
・作文の書き方・コツ(その1)苦手イシキ払拭編(3月20日)
・作文の書き方・コツ(その2)苦手イシキ克服編(3月26日)
・説明文・論説文の読み方・解き方 その1(3月26日)
・説明文・論説文の読み方・解き方 その2(例文あり)(4月5日)
・物語文・小説文の読み方・解き方 その1(5月3日)
・物語文・小説文の読み方・解き方 その2
・物語文・小説文の読み方・解き方 その3
・選択式なら満点が取れる! 実際のテストの「解き方」
・保護者の方にも読んでほしい「成長」に関わる国語の大切さ
・文章力をさらに磨きたい人のためのオススメ書籍 その1
・文章力をさらに磨きたい人のためのオススメ書籍 その2
※本コラムの転載行為や本コラムを元にしたYouTube等での配信行為は、これを全て固く禁じます。
■[例文]ウイルスはトイレからやってくる?
今回の例文はまさかなのオリジナル文です。
最初に素の文章を読んでいただいて、そのあと、作文のルールや、どこがまさかなの言いたいこと、主張なのかについてお話していきます。
ウイルスはトイレからやってくる?
まさかな
皆さんを怖がらせるつもりはないのですが、4月4日(土)の都内の感染者数は120人と、初めて1日の感染者数が100人を超えました。
3月25日(水)の感染者数が41人でしたから、そこから10日近くで約3倍に増えたことになります。
個人的に気になっているのが、数の増加ももちろんですが、感染経路(かんせんけいろ)が不明の方の数・割合が、どんどん多くなっているということです。
感染経路が不明、というのは、ようするに「どこでウイルスに接触して感染したのかがわからない」ということです。
で、まさかながずっと気になっているのは、「トイレが感染スポットになっている例があるのではないか?」ということです。
まず最初に、新型コロナウイルスについて、簡単(かんたん)におさらいをしておきましょう。
新型コロナウイルスが、人から人にうつるルートとしては、今現在「接触(せっしょく)感染」と「飛沫(ひまつ)感染」があるとされています。
ほかの感染ルートとしては「空気感染」がありますが、今回のウイルスに関しては、とりあえず今の段階ではそれはないということです。
ウイルスは一般的には、口や鼻、そして目から体内へと入り込みます。
「接触(せっしょく)感染」というのは、ウイルスを持った人が、ウイルスを持っていない人と、同じ場所で一定時間・一定の距離(きょり)で利用することで、ウイルスを感染させてしまうケースです。
これを防ぐために盛(さか)んに言われているのが「濃厚接触(のうこうせっしょく)を避(さ)けなさい」というもので、厚生労働省のホームページでは、約2メートルの距離を空けるようにと書かれています(時間については書かれていませんでした)。
最近テレビ番組で、出演者と出演者とのあいだがミョウにスカスカなときがありますが、これはそうした指示を反映(はんえい)させたものです。
ただし、これはあくまで「目安」です。3メートル離れていても4メートル離れていても、ウイルスがうつってしまう場合はありえます。
そのため、東京都の小池知事が呪文(じゅもん)のように繰り返しているのが「3密(みつ)」「3つの密(みつ)」です。
「密閉(された空間で人と会うこと)、」「(人の)密集(した場所へ行かないこと)」「(人と)密接(な距離をとらないこと)」を略したものです。先に書いた「濃厚接触」をさけるための方法をわかりやすい(?)言葉に置き換える試(こころ)みです。
つぎに「飛沫(ひまつ)感染」です。「飛沫」というのはしぶき(もっと簡単にいうと「液体(えきたい)」でしょうか)のことです。
ウイルスに感染した人の咳(せき)やくしゃみによって、ウイルスが入った「つば」が飛び散ることで、新たに感染する人を増やしてしまうことです。
(ちょっと気持ちの悪い想像ですが)「つば」がほかの人の口に直接入る、というのはすこし考えにくいですが、たとえば服や肌について、そのまま何かの拍子(ひょうし、タイミング)に口や目に入っていくということが考えられています。
こうした感染について、すこしでも被害を食い止めるために言われているのが「咳エチケット」です。具体的には、「咳・くしゃみをする際、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖、肘の内側などを使って、口や鼻をおさえましょう」というものです。
もうすこし説明します。コロナウイルスの感染から症状がでてくるまで、約2週間かかると言われており、そして人によっては、約2週間たっても、感染しているのにその症状が表にでてこない人もいます。
ふつうに出歩いている人が、すでにコロナウイルスに感染し、ウイルスを運んでいる可能性は、残念ながら大いにあるわけです。
さて、トイレです。(きちゃない話で申し訳ないですが)ウイルスは便にも付着(ふちゃく。くっつくこと)すると言います。クルーズ船の報道(ほうどう)のときにも話題になりました。
当然、用を足せば便は流すものですが、ウイルスのすべてが流れていくわけではありません。男性のおしっこは、立ってする場合には、どんなに注意しても周りに飛び散ってしまうものです(千鳥のノブさんが出演しているトイレ洗剤のCMを見た人もいるかも知れません)。
会社、ビルや駅やお店などで使える、無料のトイレ。もちろん清掃が定期的に入っているところもあるとは思いますが、そうではないところもやはりあるでしょう。仮に清掃が入っていても、それがウイルスを落とすのに十分なものなのかわかりません。
先に書いた感染者に対する感染経路の確認の際も、どの人物と会ったか、通勤経路などはどのようにしているか、は聞いても、いつどこのトイレを使ったか、は聞いていないのではないでしょうか。聞き取りを元に使用した消毒を行ったというニュースも聞いていません(ただし、この部分はまさかなの推測(すいそく)の部分が大きいので、それは言っておきますね)。
こう聞くと、「トイレで流されなくても、清掃が入らなくても(次の人がそのトイレを使うまでに)コロナウイルスは死滅するのでは?」という意見も出てくるかもしれません。
しかし、アメリカの研究では「コロナウイルスはプラスチックやステンレス鋼の表面で最長で3日間生きられることを示す分析結果が出た」という報道もあります(3月19日 CNN)。感染経路となるのには、十分な期間と言えるでしょう。
加えて、私自身最近よく観察するようになって驚(おどろ)くのですが、トイレに入っても手を洗わずに出ていく人が案外(あんがい)多いのです。
でていった先で女性と手を繋(つな)いで歩き出すのを目の当たりにして「うーわー…」と思ったりすることもしばしばです。
トイレが今回の新型コロナウイルスの感染経路として機能する、というのは残念ながらあまり飛躍(ひやく)した発想(はっそう)ではないように思えます。
正直今からでは遅すぎるかもしれませんが、感染者が使用したトイレの特定とその消毒作業、(そして男性としては複雑ですが、トイレは可能な限り「座ってできる」環境を作ること)は、やるに越したことはないのかも知れません。
──────────────
ここからは蛇足(だそく)・そしてお願いになります。まだまだ安心できない状況(じょうきょう)ですが、学校が再開された地域もあるようです。
まさかなは基本的には「ゴールデンウィーク明けまで休校を続けたほうが良いんじゃないか派」なのですが、再開されている以上、行かないわけにもいかない、という部分もあるかと思います。
最初に書きましたが、ウイルスが体内に入る場所は、基本的・そして最終的には「口、鼻、目から」、で、「口・鼻・目」にウイルスを運ぶのは「手」です。
だからこそ手洗いは大事。あなたがあなたを守ることのできる、本当に最後の砦(とりで)です。「自分も感染している(かもしれない)」という前提で行動し、手洗い・うがいは、ほんとにやっていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
あとで実際(じっさい)の原稿用紙で見てみるとどうなるか、的な画像をあげようと思っているのですが、6枚分になってしまいました。
必要最低限なつもりとはいえ、これでは例としては多すぎて失格かもしれませんね、ごめんなさい。
とはいえ、お話を進めて参りましょう。
※CNNのニュースについてはこちらから。
■作文のルール
まずは、まさかなの主張について考える前に、作文のルールについてざっと確認していきましょう。
・一行目はタイトル。
・二行目は名前・クラス・学年。
・三行目から本文。
・段落(ひとかたまりになった文章のこと)の最初の一文字は空白にして、2文字目から書き始める。
・かっこ(「」や()など)は一文字であつかう。
といったところでしょうか。細かいルールは皆さんの通う学校や習う先生によっても違うでしょうから、そこはその先生の教え方にしたがってください。
作文のルールについては、また別のコラムでまとめたいと思います。
■筆者の主張はどこにある?
さて、この説明文・論説文でまさかながいいたかったこと、つまり主張は、「新型コロナウイルスの感染経路はトイレにあるのではないか?」という部分にあります。
まあわかりやすかったかと思いますが、ではふだん教科書やテスト問題を読む時、主張を探すためにどこに注意していればいいかというと、だいたいの場合、1)タイトル、2)文章の最初のほう、3)文章の最後のほうに繰り返し出てくることが多いです。今回の文章でもそのような作りにしてあるので、もう一度読んでみてください。特に文章の最後のほうに出てくる主張。すこしぼかすような書き方にしてあるのですが、どこにあるかわかりますか?
こうした文章の書き方はけっこう決まっていて、それはなぜかと言えば、それが一番読んでいる人に伝わりやすい「型(かた)」だから、なのです。
とはいえ、教科書に出てくる説明文・論説文を書いている人には、そうした文章の「型」を習わずに書いている人もいるはずで、そうした場合は読みこなす、つまり筆者の主張を読み解くのが難しい場合もありますし、わざとそうした文章をテストに使っている場合もあります。その場合でも、「文章の最初のほうに、疑問形(ぎもんけい)の形で筆者の主張がでてくる」というのは有効です。
ぜひこれを思い出しながら、「読み解く」ということをやってみてほしいと思います。
■「反対意見」はどこにあった?
さて、前回のコラムでは、「優れた説明文・論説文には、必ず筆者の主張と反対の意見も盛り込まれています。なぜなら、その反対意見を否定することによって、自分の意見の正しさを増すことができるからです」というお話をしました。
「ショートケーキが大好き」なAくんのお話の件(けん)です。覚えていますか?
今回のコロナウイルスの話に、では「反対意見」はあったでしょうか?
実はあったんです。
こう聞くと、「トイレで流されなくても、清掃が入らなくても(次の人がそのトイレを使うまでに)コロナウイルスは死滅するのでは?」という意見も出てくるかもしれません。
という部分。これが、「筆者とは反対の意見」の部分になります。
■接続詞(せつぞくし)はちゃんと読めていたか?
説明文・論説文を読むとき、もうひとつ重要(じゅうよう)なポイントになるのが、「接続詞」だとも言いました。注目(ちゅうもく)しながら読むことができたでしょうか。
今回使われた接続詞や、接続詞的な役割(やくわり)を果たしていた言葉を、ざっと書き出してみます。
・が(「しかし」的な意味合いの「が」)
・から(「だから」的な意味合いの「から」)
・ようするに
・で、
・まず
・ただし、
・つぎに
・たとえば
・そのため、
・さて、
・もちろん
・しかし
ざっと抜き出すとこんな感じです(ここも、あとで実際の文章にマークした画像をアップしたいと思います)。ぶっちゃけて言いますと、「いますぐにこうした文章の読み方を身につけなければダメだぞ!」というつもりはありません。
次の次の回で詳しくお話しするつもりですが、説明文・論説文、そして小説文・物語文を決められた時間内で読み込み、筆者の主張をさがし…接続詞をさがして…なんていうのは、「慣(な)れ」ができないとできません。あるていど、「ちゃんとした」経験(けいけん)を積(つ)まないとできるようにはならないのです。
ですが今回一つだけ、見つけてほしい! という接続詞があったとするなら、前の段落(だんらく)でお話しした「反対意見」の直後(ちょくご=すぐあと)にあった「しかし」は、ぜひ見つけておいてほしかった接続詞です。
(べつに今回見つけられなかったとしても気にする必要はありません。ただもし、見つけられなかったことで悔(くや)しい思いをしている人がいたら、その悔しさを忘れずに、できればちゃんと向き合っていってほしいと思います)
この「しかし」の前には「反対意見」があり、「しかし」という接続詞には逆接(ぎゃくせつ)、つまり文章の流れを反対方向に変える力を持っており、ということは、「反対意見」の「反対方向」ですから、そこには筆者の主張、またはそれに近い方向性の文章が置いてある、ということになるわけです。
ちなみにその「しかし」のあとに、自分の主張を高めるためにCNN(アメリカのテレビ局)のニュースを置いているのも、意図的(いとてき)なものです。
「公的な団体」が発した、しかも「研究データ」という、二重に「客観的(きゃっかんてき)」なお話を持ってくることで、読んでくれる人の筆者の主張に対する納得感を高めたい、という狙(ねら)いがあるわけです。
■まとめ
文章で説明するだけだとわかりにくいかなと思い、実際に自分で説明文(らしきもの)を書き、それを元に説明すれば理解が深まるかな、と思ったのですが、いかがだったでしょうか。
ちなみに、最後のほうで「蛇足(だそく)ですが」と付け加えた部分がありましたが、蛇足というのは、語源(ごげん)としては文字通り「蛇(へび)の足」で、「いらないもの」という意味をもった言葉です。
なぜあの部分がいらないかというと、説明文・論説文に盛り込まれるべき主張というのは、基本的には一つだけなんですね。
今回の説明文の主張は、くりかえしお話ししてきたように「新型コロナウイルスの感染経路が不明な人のルートにトイレがあるのではないか?」というものでした。
蛇足の部分でお話したかったのは「とにかく手を洗ってくれ!」ですので、主張がふたつになってしまう。「こいつは結局何が言いたいんだ?」という混乱を起こさせてしまい、結局は筆者が伝えたいことがちゃんと伝わらなくなってしまうわけです。
ただまあ、どうしてもお伝えしたかったことだったので、「蛇足ですが」と、付け加えさせていただいたのでした。
というわけで、今日はここまで。
次回も読んでくださったら、嬉しく思います。
ではでは( ˙꒳ ˙ )ノシ。
※本コラムの転載行為や本コラムを元にしたYouTube等での配信行為は、これを全て固く禁じます。
【小・中・高校生向け/作文・国語シリーズ・目次と予定】
・作文の書き方・コツ(その1)苦手イシキ払拭編(3月20日)
・作文の書き方・コツ(その2)苦手イシキ克服編(3月26日)
・説明文・論説文の読み方・解き方 その1(3月26日)
・説明文・論説文の読み方・解き方 その2(例文あり)(4月5日)
・物語文・小説文の読み方・解き方 その1(5月3日)
・物語文・小説文の読み方・解き方 その2
・物語文・小説文の読み方・解き方 その3
・選択式なら満点が取れる! 実際のテストの「解き方」
・保護者の方にも読んでほしい「成長」に関わる国語の大切さ
・文章力をさらに磨きたい人のためのオススメ書籍 その1
・文章力をさらに磨きたい人のためのオススメ書籍 その2